メンバーブログ(2025年10月)
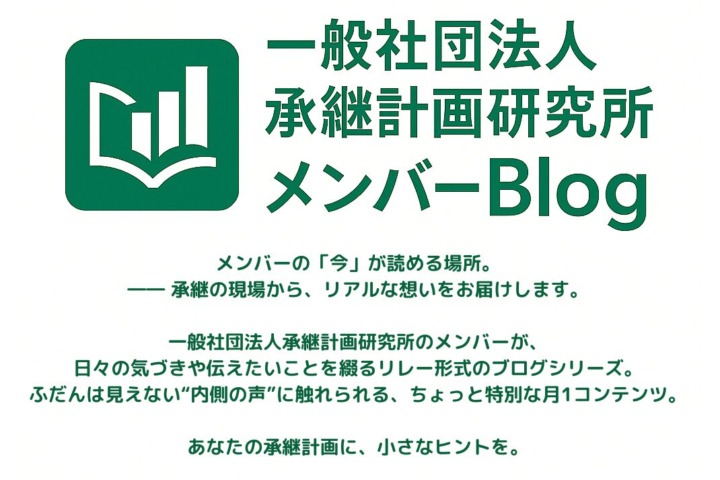
【事業承継における“経営の承継”の難しさとその背景】
一般社団法人承継計画研究所では、さまざまな企業様の事業承継に関するご相談を受けております。その中で、ある株式会社の事例をご紹介します。
こちらの会社様では、親族内承継によって二代目社長が誕生しました。新しい社長は、同業他社で現場の仕事を10年間以上経験され、実家の事業を継ぐために実家の会社へ入社したという経歴をお持ちです。
幸いにもこちらの会社の顧問税理士は法人税や所得税だけでなく資産税にも知見をお持ちであったが故に、先代社長から二代目社長に対する「株式の移転スキーム」についても良く熟知されており、オーナー一族様は事業承継にかかる承継コストを適法に抑制しながら、会社の主たるオーナーを先代社長から二代目社長へ移しておりました。故に自社株の承継問題については滞りなく進んでいたものの、会社経営の方では大きな問題にぶち当たりました。
この二代目社長は、同業他社で現場の仕事経験があったものの、経営に関する経験は特段持ち合わせておりませんでした。また先代社長は、現場仕事をこなすうちに自然と会社が大きくなってきたため、経営について特段勉強はしてきておらず、現場で身に付けた感覚により会社を回してきておりました。それ故に先代社長は現場社員と同じ目線で仕事を続けてきたため、現場社員と考え方が一致しており、大きな支持を集めておりました。
しかしながら会社が大きくなったり時代が変わったりしてくると、仕事のやり方の変化、働き方改革、コンプライアンス等、様々な経営課題が出てきます。このタイミングで二代目社長が誕生し、二代目社長は先代社長よりこれらの経営課題について対応するように命を受けました。とはいえ、二代目社長も会社経営の経験がないため、いくら経営に関する本を読んで経営について勉強したところで、すぐには自社に合った経営の舵取りをすることが出来ません。
二代目社長は日々会社の将来のことを考えて、今までの先代社長と異なる経営方針を打ち出したりもしますが、必ずといっていいほど既存の従業員の理解を得ることが出来ず、むしろ反発を受けてしまいました。更に先代社長までもが、二代目社長が自分のやり方と違うやり方を経営方針へ掲げると、どこかいい気持がしないようで、先代社長までもが既存従業員と共に二代目社長に対して反発しておりました。その結果、二代目社長は会社の存続、お客様及び従業員の幸せを第一に考えて動いているのにも関わらず、いつの間にか社内では四面楚歌の状態です。
このような原因は人間の心理が大きく影響しているものと思われます。まず、先代社長と既存従業員との間には長年における強い信頼関係が築かれているという事実があります。そこへ外から来た新たな二代目社長が加わり、今までと違うやり方を掲げることは当然に面白くなく感じるハズです。
正直なところ会社の経営は「赤字を出さないこと(=利益を出すこと)」や「法令順守(コンプライアンス)」等の基本的なところを抑えていれば、後は経営者のカラーの問題であり、どれも正解(経営者の数だけ経営の答えはある)であるというのが一般論だと思います。故に会社の商売がうまく進んでいるのであれば、本来会社関係者の方は素直に二代目社長の経営方針に従うべきなのです。
この辺りのいざこざは、二代目社長が会社経営について全く勉強をしたことがなく、また小さい組織での経営経験すらない状態で二代目社長へ就任したからこそ起きた問題のように見受けられます。
多くの中小企業における事業承継問題は、流通コストのかかる「株式の移転スキーム」のところにばかり注目がいきがちです。しかしながら実際は「経営の承継」についても机の上の勉強や外での経験(例:他社でチームリーダーを経験する等)が必須であり、このポイントを見落としている中小企業が多くあるように思われます。
今回の事例でも、例えば二代目社長が現場の仕事を通じて既存従業員との関係性を構築した後に二代目社長として就任したり、また新しい会社の経営方針を掲げる際も物の言い方等に気を付けていれば、もう少し円滑に経営の承継が出来たように感じておりました。
会社は組織、組織は人の集合体ですので、どの中小企業においても先代社長は「後継者教育の必要性」についてよく理解した上で、先代社長と二代目社長とで協力し合って会社の経営を承継していって頂きたいものです。経営の承継が事業承継全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。
以上
〔理事(組織承継部):山根〕

